 |
郵便局利用し遠隔健康診断 2月に旭川医大が実験へ 旭川医科大は、郵便局の高速通信網や局内のスペースを利用した、遠隔地での健康診断「一坪健康センター」(仮称)の実証実験を、来年2月に道内で始めると発表した。郵便局内に健康診断用の機器を設置。検診者が体重や体脂肪率などを量ると、郵便局の高速通信のネットワークを通じて大学側にデータが届く仕組み。(2007/12/30) |
|---|---|
| 札幌医大が"非医師"課程 札幌医大は2008年4月から、医師以外の医学・医療の専門家を育成する修士課程を大学院医学研究科に新設する。修了後の進路に製薬会社の研究職や介護施設のスタッフ、医療ジャーナリストなどを目指す。新課程は、2年間の医科学専攻修士課程で募集人数は10人。出身学部に制限を設けず、医療系大学出身者以外も対象としている。(2007/12/30) |
|
| 来年度から道立7病院で看護職を副院長に登用 道は、道立七病院の経営改革の一環として、来年度から副院長に看護職を登用することを決めた。医師が独占してきたポストに看護職をあてることで看護職全体の責任意識を高め、効率的な運営に役立てる機構改革だ。(2007/12/30) |
|
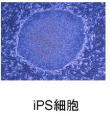 |
京大iPS細胞が2位 米科学誌サイエンスは2007年の科学進歩ベスト10を発表し、ヒトの遺伝的多様性の解明の進展がトップ、京都大の山中伸弥教授らと米ウィスコンシン大チームによるヒト人工多能性幹(iPS)細胞の作成が2位に選ばれた。 万能細胞研究に100億円超 5年間で、文科相表明 再生医療への応用期待 京都大の山中伸弥教授が作製に成功した万能細胞「人工多能性幹細胞(iPS細胞)」について渡海紀三朗文部科学相は、今後5年間で100億円超の研究費を投入する方針を明らかにした。研究者の連携のための組織(コンソーシアム)をつくるなどとする文科省の総合戦略にもこの方針が明記された。2008年度予算案の閣僚折衝で、研究推進のため文科省が求めていた10億円の追加が認められ、08年度予算案の総額が22億円になることが固まった。07年度の同細胞研究関連予算は計約2億7000万円で、約8倍の増となる。22億円は、山中教授を中心としたiPS細胞の研究態勢の強化、再生医療実現に向けて同細胞を使った治療や細胞の操作技術の開発を支援するための予算。 既にこれらとは別に、研究拠点の「iPS細胞センター」が置かれる京都大の「物質?細胞統合システム拠点」の研究環境整備のために14億円が計上されている。 京大にiPS研究センター 文部科学省は、世界で初めて作製した万能細胞「人工多能性幹細胞(iPS細胞)」の研究推進策として、京大に研究拠点「iPS細胞研究センター」を整備することなどを柱とした総合戦略案をまとめた。 また、iPS細胞を用いた治療法の開発を加速させるため、関連研究の公募を年内に開始。iPS細胞をめぐる国内、海外での特許取得も支援する。来年度以降は新研究事業などで財政面での支援を拡充する。 京大に万能細胞研究拠点 渡海紀三朗文部科学相は、京都大の山中伸弥教授が作製に成功したさまざまな細胞になる可能性を持つ万能細胞の一種、人工多能性幹細胞(iPS細胞)について、京都大に拠点を設けて研究を進める構想を明らかにした。 <今後の展開> 今回の成果により、ヒト成人の皮膚細胞からもiPS細胞の樹立ができることが分かりました。脊髄損傷や心不全などの患者体細胞からiPS 細胞を誘導し、さらに神経細胞や心筋細胞を分化させることにより、倫理的問題や拒絶反応のない細胞移植療法の実現が期待されます。またこれらの細胞は、疾患の原因の解明や新治療薬の開発に大きく寄与するものです。(2007/12/30) |
| 山中 伸弥教授(物質−細胞統合システム拠点/再生医科学研究所)らの研究グループは、ヒトの皮膚細胞からES細胞(胚性幹細胞)と遜色のない能力をもった人工多能性幹細胞(iPS細胞)の開発に成功しました。ヒトiPS細胞は患者自身の皮膚細胞から樹立できることから、脊髄損傷や若年型糖尿病など多くの疾患に対する細胞移植療法につながるものと期待されます。またヒトiPS細胞から分化させる心筋細胞や肝細胞は、有効で安全な薬物の探索にも大きく貢献すると期待されます。(2007/11/21) | |
財団法人日本医療評価機構の11月19日新規・更新認定道内分は、恵佑会札幌病院(白石区) がV5.0で新規取得、網走厚生病院(網走)が新規取得いたしました。 (2007/12/30) がV5.0で新規取得、網走厚生病院(網走)が新規取得いたしました。 (2007/12/30) |
|
 |
処方せん様式変更、後発医薬品への変更不可の場合は明記 後発医薬品使用促進のため、、(1)処方せん様式の変更(2)「変更不可」欄に署名等がない処方せんに記載された後発医薬品の薬局での銘柄変更調剤(3)薬局の調剤基本料の見直しと後発医薬品の調剤率を踏まえた評価-など、7項目の具体的な施策が示された。処方せんの様式は、後発医薬品に変更すると差し支えがある場合に、「後発医薬品への変更不可」欄に署名などをする形に、変更される。(2007/12/30) |
| 緊急医師派遣の第2弾が決定 厚生労働省は10月29日、「地域医療支援中央会議」を開き、国レベルで医師不足地域に医師を派遣する「緊急臨時的医師派遣」の第2弾の派遣を決めた。緊急医師派遣が決まったのは北海道、和歌山県内の計3病院だが実質は北海道のみ。医師確保などに苦慮する都道府県の要請に応じ、厚労省の委嘱した地域医療アドバイザー3人を派遣することも了承した。派遣されるのは、北海道の留萌市立病院と市立根室病院。留萌市立病院は、循環器科1人、脳神経外科3人、外科1人の医師派遣を要請した。中央会議は今回、循環器科医の確保を最優先し、11月からの5カ月程度、市立旭川病院から循環器科医1人の週2回の派遣を受け入れることが決まった。産婦人科医1人を派遣要請した市立根室病院には来年4月から6カ月程度、応募医師1人の勤務が内定した。北海道の北海道社会事業協会岩内病院では5月から内科医が不在だったが、複数医師によるローテーション方式で常勤医1人を確保することができたとの報告がありました。 (2007/11/6) |
|
| 札幌医科大 医学部定員増で奨学金 連動地域枠が10人に 北海道医療対策協議会の地域医療を担う医師養成検討分科会が開催され、札幌医科大の医学部定員を来年度から5人増員した上で、道が来年度から実施する地域枠と連動させた奨学金制度の対象とすることを了承した。 |
|
| 病院勤務医の負担を軽減、診療所の夜間延長に加算 来年度の診療報酬改定で厚生労働省は、開業時間を夜間まで延長した診療所に診療報酬を手厚く加算する方針を固め、中央社会保険医療協議会(中医協)に提案した。地域の開業医に症状が軽い患者の診察を分担してもらって、病院勤務医の負担を軽くする狙い。勤務の過酷さから、地域の拠点病院などで勤務医の退職が相次いだことが「医師不足、地域医療の崩壊につながった」と指摘されており、改定案は勤務医の待遇是正策の一環。診療データ入力や文書作成など、診療行為以外の煩雑な作業を肩代わりできる事務補助員の病院への配置も、報酬で上乗せする方針を示した。本来なら、普通医師が一人か少数で行っている診療所が夜間もやるのは反対のような気がするのですが、やはり異常状態なのでしょうかね。 (2007/11/6) |
|
| 公立病院改革の素案、利用率3年連続70%未満で診療所格下げや病床数削減 地方自治体が設置する公立病院の経営改善策を検討している総務省の有識者懇談会は、病床利用率が3年連続で70%未満の病院に対し、診療所への格下げや病床数の削減など抜本的見直しを求めることを盛り込んだ経営改革ガイドラインの素案をまとめました。 総務省はこれに基づき自治体が具体的な改革プランを2008年度中に作成するよう促す。各自治体の改革が進むよう地方交付税などで財政支援する方針。各病院は3年以内に経営効率化を進め、一般会計からの補てんも含め黒字化を目指すとした。年度平均の病床利用率や経常収支比率などの経営指標について各自治体が数値目標を設定。特に病床利用率が「3年連続70%未満」の病院は、診療所(20床未満)への転換など改善策を講じることが適当とした。ずっと懸念されている小樽市立病院の行く先は----。(2007/11/6) |
|
| 財団法人日本医療評価機構の10月01日新規・更新認定道内分は、札幌里塚病院(清田区)、井上病院(中央区)がV5.0で更新取得、網走厚生病院(網走)が新規取得いたしました。 (2007/11/2) | |
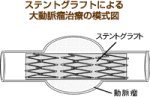 |
開腹せずに「腹部大動脈瘤治療」道東でただ1人 市立釧路総合病院の心臓血管外科部長、上久保康弘医師(44)が道東では初めて、開腹せずに腹部大動脈瘤の治療ができるステントグラフト内挿術の認定医師としての資格を受けた。ステントグラフトは足の付け根からカテーテルで血管内に挿入できる管状のもので、、日本でもこの4月から厚生労働省の認可が下りました。ステントグラフトは,人工血管にステントといわれるバネ状の金属を取り付けた新型の人工血管で,これを圧縮して細いカテーテルの中に収納したまま使用します.カテーテルを,患者さんの脚の付け根を4〜5cm切開して動脈内に挿入し,動脈瘤のある部位まで運んだところで収納してあったステントグラフトを放出します.この方法だと,胸部や腹部を切開する必要はありません.放出されたステントグラフトは,金属バネの力と患者さん自身の血圧によって広がって血管内壁に張り付けられるので,外科手術のように直接縫いつけなくても,自然に固定されます. (2007/10/29) |
 |
道内初、室蘭・新日鉄病院が女性専用病棟を開設 新日鉄室蘭総合病院はこのほど、男性の目を気にせずに入院できる女性専用病棟を3階に開設、運営を開始した。女性患者からは「洗面時のパジャマ姿を男性に見られる」「病棟の廊下から見知らぬ男性にのぞかれる」「昼間でもベッドカーテンを閉めないと」など苦情や要望が多く聞かれるが、こういった問題を解消する先進的な取り組みですね。 (2007/10/24) |
| ついにあのカプセル内視鏡を北斗病院(帯広)本格導入 北斗病院(帯広)はは錠剤のようにのみ込んで小腸の状態を観察できる「カプセル内視鏡」を導入しました。道内では北大などで試験導入の例はあるが、本格導入は初めて。カプセル内視鏡はイスラエル製で口からのみ込み、肛門から排出されるまでの約八時間、毎秒二枚、計六万枚の画像を撮影。患者の腰に装着した受信装置に画像データを送り、医師はパソコンなどを使って画像を見る。使い捨てで、検査費は患者側の三割負担の場合、約三万円。 (2007/10/24) |
|
 |
医師承諾なしでも薬剤師が後発医薬品の銘柄変更可? 厚生労働省は、後発医薬品普及策の案として医師が銘柄を指定して処方した後発薬について、患者の同意があれば、薬剤師は医師の承諾がなくとも同じ効能の別銘柄の後発薬を調剤できるようにすることや、省令の保険医規則に後発薬処方を医師の努力義務とする規定を盛り込む--などの内容を示しましたが、日本医師会は「医師の処方権を侵害する」と強く反発しています。 (2007/10/24) |
| 400床以上に「明細書」の発行を義務付け 厚生労働省は、IT化が進んだ400床以上の大病院に対して、患者の求めがあった場合に医療費の明細書の発行を義務づける方針を固めた。2008年4月にオンライン請求が義務化されることから、明細書を発行する基盤も既に整備されていると判断。実費徴収を認めつつ、発行を希望する患者への義務付けを決めました。現行制度では患者が求めても発行の義務はない。 (2007/10/24) |
|
| 日鋼記念病院が「救急救命センター」を休止へ。医療法人社団カレスアライアンス(室蘭)が経営する日鋼記念病院(室蘭市新富町)は十一日、医師不足から、高度救急医療(三次救急)を担う「救急救命センター」を休止する方針を固めた。救命救急センターの休止は全国初。日鋼記念病院は今年九月、同社団の西村昭男理事長の解任に伴い、前院長を含め西村氏に近い医師ら五人がすでに退職。十一月末までにさらに五人の退職が決まっており、医師は六十九人にまで減る見通しのため救急救命センターの機能維持は難しいとの判断に。同社団の混乱は、同社団が経営する天使病院(札幌)の別法人への移管問題が発端。移管を提案した西村前理事長に病院職員が反発、天使病院の産婦人科医師六人が退職を申し出る事態になった。その後、九月の臨時社員総会と理事会で西村氏が解任され、西村氏に近い日鋼記念病院の医師の退職が相次ぐなど、混乱が続いている。 当法人は、今年八月に財団法人日本医療評価機構の8月20日新規・更新認定道内分で、カレスアライアンス(旧日鋼記念病院 室蘭がV5.0で更新取得いたしました。その中に「組織運営の基盤整備は極めて優れた状況といえ、模範的なレベルに達成し得ている。 実際の組織マネジメントにも優れた取り組みがなされている。すなわち、組織内情報の伝達機能を最重要視し会議形態の複層化の確立、情報伝達のシステム整備に力を注いでおり、組織決定事項の伝達などにその成果もみえている。これらの情報化のプロセスのなかで情報管理のあり方についても先駆的な取り組みがなされている。 上記のよく整備・充足された状況が認められる基盤には、毎朝開催されている病院幹部による総合企画調整委員会で病院のあらゆる事項を討議討論の場として活用されていること、それに基づく各種委員会の活発な活動があること、が存することを大いに評価したい。」というような評価がされています。どうなんでしょうかね。格付けでは、こういった騒動から既に格付けがさがっているようですが。 (2007/10/15) |
|
| 日鋼記念病院が運営母体の理事長交代劇を受け、院長を含め医師10人の退職が決定。循環器科を含む2診療科が休診、救命救急センターの休止の可能性も浮上するなど、地域医療に大きな影を落としている。 | |
| 一般とは逆?診療報酬6千万円徴収漏れの自衛隊病院 防衛省が運営し、一般患者も受診できる5カ所の自衛隊病院で、診療報酬を少なく請求していたことが会計検査院の調べで分かりました。看護師数が充実しているにもかかわらず「有事の際は数を確保できなくなる」として実際より少ない看護師数で診療報酬を計算していたといい請求漏れは06年度で計6100万円に上るとのことです。医師や看護師が少ないにもかかわらず多く請求して問題になっている現状から見て、こんな逆なこともあるんですね。というか、採算は関係ないんでしようね。 06年度の診療報酬改定では、入院基本料を定める看護師の配置基準が変わり、最も報酬が高かった「10対1(患者10人に看護師1人)」に「7対1」が加わった。厚生労働省によると、10対1の場合の入院基本料は1日1万2690円、7対1は1万5550円で、病院はより高い報酬を患者と公的医療保険の保険者(運営団体)に請求できるようになった。 (2007/10/15) |
|
 |
舛添厚生労働相、新薬の承認にかかる期間を米国並み1年半に大幅短縮へ 舛添厚生労働相は、「新薬の承認にかかる期間を米国並みにする」と述べ、海外で新薬が出てから日本国内で販売承認されるまでの期間を現在の約4年から1.5年程度に大幅に短縮する考えを示した。新薬の審査にあたる人員を約400人に倍増するなどして、2011年度の実現を目指すという。 (2007/10/15) |
| 38自治体病院が診療所への規模縮に 道は、道内94カ所ある自治体病院のうち38病院について、診療所への規模縮小の検討を求める考えを明らかにしました。また38病院以外でも、財政状況が厳しい市立赤平総合病院、市立小樽病院、市立美唄病院など9病院について、「規模を適切に見直す必要がある」などと明記。他の医療機関と連携し、規模縮小も含め検討するよう促している。自治体病院等広域化・連携構想は、赤字経営や医師不足に苦しむ自治体病院を三十区域ごとに再編するのが狙い。 (診療所化の検討を求めた38病院) 松前町立松前病院、森町国保病院、奥尻町国保病院、厚沢部町国保病院、乙部町国保病院、八雲町熊石国保病院、国保由仁町立病院、黒松内町国保病院、京極町国保病院、幌加内町国保病院、豊浦町国保病院、白老町立国保病院、平取町国保病院、新冠町国保病院、新ひだか町立静内病院、新ひだか町立三石国保病院、上川町立病院、国保町立和寒病院、上富良野町立病院、国保中富良野町立病院、遠別町立国保病院、天塩町立国保病院、幌延町立病院、猿払村国保病院、豊富町国保病院、興部町国保病院、雄武町国保病院、士幌町国保病院、鹿追町国保病院、大樹町立国保病院、広尾町国保病院、池田町立病院、本別町国保病院、足寄町国保病院、市立釧路国保阿寒病院、標茶町立病院、標津町国保標津病院、羅臼町国保病院 |
|
 |
妊婦緊急搬送受け入れで診療報酬加算 厚生労働省は、妊婦の救急搬送の受け入れを拒否する病院が相次いだ問題を受け、緊急搬送を受け入れた病院に診療報酬を加算する方針を中央社会医療保険協議会に提示し2008年度の次期診療報酬改定での実現を目指す。「緊急搬送受け入れ料(仮称)」を診療報酬項目として新設。帝王切開が必要な分娩や重い妊娠高血圧症など保険適用の対象事例だった場合は、受け入れた件数ごとに報酬を加算する方向という。しかし、受け入れ後に大きな異常がみられず自然分娩に至った場合は、現行通り保険対象外とし、受け入れ料も適用しないようで目先に人参をぶらさげたようなこの案は一体どの位の効果があるのか疑問におもってしまいます。もっと別な対抗策が必要では---。 (2007/10/9) |
 |
国公立の専門病院25施設でのがん生存率:分析結果を公表 国公立のがん専門病院などでつくる「全国がんセンター協議会」(全がん協、30病院)は4日、加盟施設の胃がん、肺がん、乳がん、大腸がんの5年生存率の分析結果を公表した。このうち同意を得られた15施設については施設名を公表しました。研究班の猿木信裕・群馬県立がんセンター手術部長は「患者のがん進行度は、病院によってばらつきがある。生存率は一つの目安であり、数字だけで比較せず、治療について医師と話すときの資料にしてほしい」とのことです。確かに一様には比較できませんが、だからといって知らせないのではなく、こういったことの積み重ねが必要なのでしょうね。トラブルも起きるのはいなめませんが。 (2007/10/9) |
 |
札幌医科大学医学部付属病院(中央区)でコンビニ開設 道内の民間病院でもよりよい利便性の実現ということでコンビニの開設が増えてきていますが、札幌医科大学医学部付属病院(中央区)も旭川医科大学(旭川)に続いての8月のスターバックスコーヒーショップの開設に加えてファミリーマート札幌医大病院店がオープンいたしました。 医師/環境 1 (2007/10/9) |
| みずうち産婦人科(旭川)は、ISO9001の認証を取得いたしました。 医師/環境 1 (2007/10/2) | |
 |
新病院の巨額起債申請!第1回目は道が協議を先送り!小樽 小樽市が強硬に進めている築港地区での新市立病院建設のための資金調達の起債(地方債)市立病院の患者数の減少などから、今後の病院経営状況の推移を見守るとして、起債協議を異例の先延ばしにした。詳細は小樽ジャーナルをご覧ください。 (2007/9/25) |
 |
一転、厚生労働省が規制緩和で診療科名を大幅拡大 厚生労働省は、医療機関が広告などで使える38の診療科名を26に整理し、新たに「総合科」などを加える案を、医道審議会診療科名標榜部会に提出するなどの動きをみせていましたが、学会や患者団体の反対にあい、検討をかさねていましたが、今度は一転、現行より大幅に拡大できるよう、名付け方のルールを規制緩和する制度を導入することを決めました。現在は、診療科名は、医科が33種、歯科が4種、麻酔科の計38種に限定されています。新ルールは臓器や身体の部位、症状、疾患、患者の特性、診療方法の名称と、内科、外科、歯科のいずれかを組み合わせて表記できる。「呼吸器内科」「神経内科」「気管食道外科」「矯正歯科」などが可能になりますが、かえって分かりにくくなる小児科、精神科、アレルギー科、リウマチ科などは、単独での使用を認める方針です。本末転倒?好き勝手につけられるのはどうですかね? (2007/9/25) |
 |
マゴットセラピーとは、治癒しにくい四肢潰瘍に対し無菌マゴット(ハエ幼虫、ウジ)を用い治癒を促す治療法です。 マゴットセラピー = ウジムシ治療 =Maggot Debridement Therapy(MDT) 生物的デブリードメン( Biological Debridement) の別名もあります。ウジを使った治療は、古代マヤ文明や豪州先住民、東南アジアなどで古くから行われていたようだ。欧米でも、負傷した兵士の傷が、ウジがわくほど早く良好に回復したことから、20世紀前半までに普及したが、抗生物質の登場でしだいに廃れた。しかし1990年代から薬剤耐性菌対策で見直され、床ずれなども含め、30か国以上、2万人以上に行われた。英、米、豪、独、イスラエルでは保険も適用され、従来の治療法より安く済むという。日本では今のところ、研究費か、全額患者負担で行う自由診療の扱いだが、約30施設で行われ、関心が高まりつつある。費用は1回の処置で3万円前後が目安となる。現在、道内でこの治療を行っているのは、函館中央病院形成外科 木村医師(函館)だけです。 マゴット治療ホームページ ・専門外来 (2007/9/25) |
 |
医療法人社団カレスアライアンスは西村理事長の解任動議を決議 室蘭の日鋼記念病院、天使病院などを持ち、道内でも病院経営の大手で先進的な医療と経営で知られていた医療法人社団カレスアライアンスは、臨時理事会および臨時総会を開き、西村昭男理事長の理事解任を賛成14票に対して反対5票、棄権2票で決議しました。これによって、西村理事長は、カレスアライアンスの経営から身を引き、別法人である特定医療法人社団カレスサッポロの経営に専念することになりました。新理事長には、2月に日鋼記念病院長を解任された勝木良雄氏が選出され理事長に、さらに、林茂理事が常務理事に返り咲きました。天使病院の経営権をカレスサッポロに譲渡することについては、白紙撤回されました。天使病院の経営権譲渡などをめぐりカレスアライアンスを舞台に繰り広げられた騒動でしたが、背景には何があったのでしようか? |
| 天使病院 別法人への移管を延期 天使病院の産婦人科医全員が退職する問題で、同病院を経営する医療法人社団カレスアライアンス(西村昭男理事長)は、十月に予定していた同病院の別法人への移管延期を決めた。予定されていた移管先は、西村氏が別に理事長を務める特定医療法人社団カレスサッポロ。カレスアライアンスでは理事有志が、《1》西村氏は利害関係の異なる二法人の理事長を兼ねているが、移管手続きについて説明が不十分《2》移管が産婦人科医の退職を引き起こし、地域医療を混乱させた−などと指摘。西村理事長の退任と経営移管の中止を求め、臨時理事会と社員総会の開催を要求している。カレスアライアンスは西村氏が1978年に年に日本製鋼所病院(現日鋼記念病院)院長に就任後、家庭医の育成や道内初の緩和ケア病棟の開設に乗りだし、道内地域医療の先駆者として注目を集め、日鋼記念病院(室蘭)など道内の複数の医療機関や福祉施設を経営している。 |
|
| 天使病院 産婦人科医全員が退職へ 天使病院は年間約八百件の出産を扱うほか、道内に二十五施設ある地域周産期母子医療センターに指定されていますが、診療科長を含む産婦人科医全員の六人が、九月末までに離職することが判明しました。医療法人社団カレスアライアンス(室蘭)が経営する同病院は十月、同じカレスグループの特定医療法人社団カレスサッポロ(札幌)への移管が予定されていましたが、移管に反対していた産婦人科医の前院長が八月下旬で退職し、診療科長を含む三人も「経営内容の不透明な新法人による再雇用を望まない」と病院側に伝え、九月末の離職を決め残る二人の若手医師も中核となるベテラン医師が不在のまま、高リスクの周産期医療は続けられないと、同じく九月末で離職する意思をしめしています。 |
|
| 旭川医大の「地域枠推薦入試」五十人へ大幅に拡大 旭川医大の吉田晃敏学長は勤務地限定の「地域枠推薦入試」について、十人の定員枠を早ければ○九年度入試から五十人へ大幅に拡大する方針を明らかにしました。地域枠推薦入試は同大独自の取り組みで、卒業後の道内医療過疎地での研修、勤務を条件に受験を認める。○八年度の十人は受験資格の出身地、卒業後の研修・勤務地とも道東、道北に限定。○九年度からはこれに加え、受験資格、研修・勤務地とも全道に拡大した四十人枠を増設する方向で検討。 (2007/9/18) |
|
 |
札幌市が「妊婦健診費用」の助成拡大 札幌市は10月1日から、妊娠中の母体と胎児の健康状態を診断する「妊婦健診」費用(「妊婦健診」は、妊婦の内診や血液検査、胎児の超音波検査などを定期的に行うもので、出産までに14回程度の受診が必要。医療保険の適用対象外のため、全額自己負担)の助成を現在の1回から5回に拡大する。費用助成の対象となるのは、来年1月1日以降に出産予定の人。費用助成は、各区の保健センターで配布している「受診票」を受け取り、指定の医療機関に提出する。母子健康手帳を持っている人は、手帳を持参の上、妊婦届出書に記入した居住地の区保健センターで受診票を受け取る。 (2007/9/18) |
 |
事故で植物状態患者の専門病院中村記念病院に委託 自動車事故対策機構は、交通事故で植物状態になった患者に高度な治療と手厚い看護を施して症状の改善を目指す医療を、中村記念病院に委託すると発表した。現在、この機能をもつ専門施設「療護センター」を本州の4カ所(計230床)で運営しているが、北海道と九州にはなかった。中村記念病院での患者の費用負担は保険診療に当たる治療だけでよく、それ以外の先端治療の費用は同機構が病院への委託費の形で支払う。 (2007/9/18) |
| 道の来年度創設目指す奨学金は? 道は、道内の医療機関で働く臨床研修医や医学部の五、六年生を対象に、道内の医師不足の地域で一定期間勤務することを条件にした奨学金制度を創設する方向で検討にはいりました。医大入学者向けの奨学金制度は来年度から始まるが、新たに検討している制度は、道内の病院で臨床研修を受けている研修医らに生活資金などとして奨学金を支給するもので研修を終えた後、貸し付けを受けた期間と同程度の期間、医対協が指定する地方の自治体病院などで勤務すれば、奨学金返還を免除するもので月二十万円程度を考えています。 (2007/9/18) |
|
| 医師確保へ「高額」奨学金!!! 埼玉県秩父市は市立病院などの医師不足解消に向け、医学生と研修医に1人当たり最高で総額4600万円を支給する奨学金制度を創設するための条例案を、市議会に提出した。!!!支給条件は(1)将来、市立病院か診療所に支給期間の2倍の期間勤務(2)保護者が市内に在住?の2つで大学医学部の入学時に入学金などで1000万円以内、入学後は授業料や生活費として月額40万円以内をそれぞれ支給。研修医にも月額30万円以内を支給する。勤務期間の条件を満たせば、奨学金と利子の返還は全額免除されるが、途中で退職などすれば全額返還を求められるといいますがこれほどの高額な奨学金とは驚きですね。 (2007/9/18) |
|
| 道内企業・医療法人再生に新ファンド 札幌中央病院(中央区)は、東京の病院再生ファンドキャピタルメディカと組み、病院施設の流動化による経営改善に乗り出したというニュースを7月13日にお知らせしましたが、こういった新しい動きが更に活発化してきました。野村ホールディングスが、地方の自治体病院の経営への助言や資産証券化を通じた資金調達の協力などで、事業展開を目指していく。また、北海道マザーランド・キャピタル(札幌市)は中堅以上の規模の企業や医療法人の支援を目的とした投資ファンド「北海道チャレンジファンド」を新たに設立する。総額は50億円。 (2007/9/18) |
|
 |
市立札幌病院 来春の看護師採用、例年の3倍140人 市立札幌病院は、来春の看護師採用試験で、例年の三倍以上となる約百四十人を採用する。これは、他の加熱する看護師獲得合戦を繰り広げている医療機関と同様に昨年四月の診療報酬改定で看護師の配置が手厚い病院には、入院基本料が上乗せされるようになったことが原因。患者十人に対して看護師一人を配置する「十対一」から「七対一」の新基準をつくり、入院基本料を上昇させたものです。しかし、厚生労働省では、この基準の見直しも論議されており来年はどうなるか------。 (2007/9/18) |
| 上湧別厚生病院、日高町立国民健康保険病院が診療所に 上湧別厚生病院が、9月1日から無床の上湧別厚生医院に変更になりました。今年4月の喜茂別厚生病院から医院への変更についでの厚生連の再編事業の一環です。また、日高町立国民健康保険病院(36床)が、昨年の診療報酬改定で赤字が1億4000万円となり町財政を圧迫したため、来年度から10床の有床診療所にして、経費削減を図ることになりました。 (2007/9/12) |
|
| 国立病院機構帯広病院の残業代請求訴訟、690万円支払いで和解 国立病院機構帯広病院(帯広市)に勤務していた医師(37)が、未払いの残業代約875万円の支払いを機構側に求めた訴訟は、未払いの残業代約875万円の支払いを求めていたが、機構側が解決金690万円を支払うことで札幌地裁で和解が成立しました。 (2007/9/11) |
|
 |
「小児科医療の重点化計画」21病院を指定 道医療対策協議会(会長・高橋知事)で医師不足が深刻な小児医療に対して小児2次救急を行っている計21病院を重点化病院(道内を13ブロックに分割、小児医療が充実している札幌圏を除く12ブロックで各1〜4病院を選定。現在、〈1〉手術・入院にも対応可能な「小児2次救急機関」である〈2〉一定数の小児科医が常勤している〈3〉新生児医療や小児の専門医療を提供している)に指定し、重点化病院の夜間・休日診療を開業医が支援するなどして勤務医の負担を減らし小児医療の安定を目指す。 札幌を除く十二医療圏と、重点化候補病院は以下の通り。▽南渡島・南桧山・北渡島桧山 函館中央病院、市立函館病院▽後志 北海道社会事業協会小樽病院▽南空知 岩見沢市立総合病院▽中空知 砂川市立病院▽西胆振 カレスアライアンス(旧日鋼記念病院)(室蘭市)、市立室蘭総合病院▽東胆振・日高 苫小牧市立総合病院、王子総合病院(苫小牧市)▽北空知・上川中部・富良野・留萌 旭川厚生病院、深川市立病院、市立旭川病院、北海道社会事業協会富良野病院▽上川北部 名寄市立総合病院▽宗谷 市立稚内病院▽遠紋・北網 北見赤十字病院、遠軽厚生病院▽十勝 帯広厚生病院、北海道社会事業協会帯広病院▽釧路・根室 釧路赤十字病院、市立釧路総合病院 (2007/9/11) |
 |
江別市立病院を総合診療内科医の養成拠点に 2006年、過酷な勤務状況を理由に内科系常勤医が全員が退職という異常事態で大きな問題となっていた江別市立病院だが、今年4月、内科医の負担軽減のため、あらゆる内科の初期診療の窓口となる総合診療内科を新設した。そこで道や江別市は、地域医療を志す医大卒業生や地方病院の勤務医向けの研修プログラムを設け、同病院を道内における総合診療内科医の養成拠点とする検討を始めた。 (2007/9/3) |