 |
茨城県立こども病院で子どもたちの闘病生活を応援するクリニクラウン(臨床道化師)が毎月派遣 こども病院へのクリニクラウンの定期訪問を導入しているのは兵庫や大阪など4都府県で、同院で7病院目とのことだそうですが、とても素敵なことですね。「笑うことが子どもたちの病気の回復につながり、付き添う親がリラックスする機会にもなる」と日本クリニクラウン協会(事務局・大阪市)の幹部の方が、おっしゃっていますが本当ですね。大人でも暗くなりがちの入院生活、遊びたい盛りの子どもたちにとってはとても大きな不安と苦痛の戦です。こんな活動があるということをもっと多くの人に知ってもらい、道内でも取り入れてもらいたいものですね。 (2007/8/27) |
|---|---|
 |
「道立子ども総合医療・療育センター(愛称:コドモックル)」が9月1日、札幌市手稲区に開設 これまで、高度医療は道立小児総合保健センター(小樽市)、リハビリなどの療育は道立札幌肢体不自由児総合療育センター(同区)が担っていたが不便があったためより良い環境と効率化を目指し統合することになりました。従来の2施設は閉鎖されます。生命の危険のある胎児や新生児を診る「特定機能周産期母子医療センター」▽先天性心疾患に高度な医療を施す「循環器病センター」▽科学的なリハビリなどをする「総合発達支援センター」などが設けられます。 (2007/8/24) |
| 学会・患者団体が猛反発し診療科名削減を撤回 厚生労働省が「患者に分かりやすい表記を目指す」として、今年5月に公表した基本診療科名を38から26に削減する見直し案について、同省が事実上白紙撤回していたことが分かった。診療科として表記できるのは医療法に基づき33の医科と四つの歯科、それに厚労相の許可を受けた麻酔科の計38科。現在は医師であれば自分の専門とは関係なく、どの科の看板を掲げても自由(麻酔科を除く)。(そもそも、これを認めることがおかしいと思うのですがね)そこで厚生労働省は基本診療科として標榜できる科を26に絞り得意分野の治療方法を基本診療科の下に自由に書き込めるよう“緩和”した(ペインクリニック、花粉症など『自由に書き込める』というところに問題があるとおもうのですが)しかし、基本診療科から外された学会や患者団体から見直しを求める要望が続出。厚労省は基本診療科名をほぼ従来通り表記できる“妥協案”を水面下で各学会に打診したといいます。本来、患者が分かりやすくするための案でありながら、『自由に書き込める』と余計に混乱を助長することになってしまっているのではないでしようか? (2007/8/21) |
|
| 来春導入控え、社会医療法人に法人税優遇 政府が来年4月に導入する社会医療法人制度は、公立病院に代わり地域医療の中核を担う組織として、救急やへき地医療などの実施を条件に法人税率を軽減する。一般的な医療法人の税率は30%だが社会医療法人は22%以下にする方向物品販売など収益事業の展開や公募債の発行も認める。 (2007/8/20) |
|
| 診療科名整理に患者ら反発! アレルギー科やリウマチ科などを名乗れなくする厚生労働省の方針に、「専門医を見付けにくくなる」「多くの科を渡り歩くことになる」などの患者らの反発が広がっている。 (2007/8/14) |
|
| 厚労省、診療科名の整理案・アレルギー科・心療内科・心臓血管外科などなくす! 厚生労働省は、医療機関が広告などで使える38の診療科名を26に整理し、新たに「総合科」などを加える案を、医道審議会診療科名標榜部会に提出した。同部会で今後検討する。同省案はアレルギー科、心療内科、心臓血管外科、呼吸器科などが削減案の対象となっている(アレルギーを専門とする場合は、「内科(アレルギー)」と表記することが可能)、また、新たに加えられる予定なのは、総合科、病理診断科(臨床検査科)、救急科で診療科目を減らす一方で、「乳腺」「頭痛」「ペースメーカー」など、医療機関が得意とする分野を明記することも認めており、同省は「広告の規制緩和を進めるとともに、患者の利便性を高めることができる」と説明している。 (2007/8/14) |
|
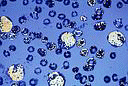 |
がん治療専門の医療従事者を養成 札幌医科大学など道内3医大と北海道医療大学(石狩管内当別町)は、がん治療専門の医療従事者を養成、院生に薬や放射線による治療法を学ばせるほか、北海道がんセンター(札幌市)など道内がん拠点病院での実習も予定、地方病院や診療所の医療従事者を対象に出前講座を開き地方で不足するがん患者向けのチーム医療体制を整える。 (2007/8/14) |
| 「新市立病院市民説明会開く!参加者から批判の声!」小樽ジャーナル 「新市立病院市民説明会開く!参加者から批判の声!」というタイトルで8月11日(土)からスタートした、「新市立病院新築に係る市民説明会」の第1回の説明会の模様が小樽ジャーナルに詳しく掲載されていますので、是非ご一読ください。あなたは、どうお考えですか?それにしても一般参加者が25名とは(これから後5回開催されるにしても関心が低すぎるようにおもいます)(2007/8/14) |
|
 |
「経営側に不信感」として天使病院 産婦人科医4人辞職へ! 地域周産期母子医療センターとして新生児集中治療施設(NICU)を設置し、緊急の帝王切開手術や低体重児の出産など、危険性の高い出産に対応し、道央の産婦人科医療の拠点となっている札幌市東区の天使病院(二百六十床)で、産婦人科医六人のうち四人が、病院を辞める意向を固めたことを北海道新聞が報道しています。医師四人は「経営母体が頻繁に変わる理由(同病院は、二○○三年に社会福祉法人聖母会(東京)から医療法人社団カレスアライアンス(室蘭)に経営が移管されたが、今年十月には、特定医療法人社団カレスサッポロ(札幌)への移管が決まっている)や、移管先の経営内容について情報開示が不十分。経営側と信頼関係が築けず、リスクが伴う周産期医療は続けられない」と退職の理由を説明しているという。残る二人も、退職を検討しているよう。病院側は「仮に一部の医師が退職しても、新たな医師を確保して診療機能は維持する」としている。 (2007/8/8) |
| 産科、小児科、救急医療の診療報酬上げ検討! 診療報酬の2008年度改定で、厚生労働相の諮問機関の中央社会保険医療協議会(中医協)が医師不足に対応し、地域医療を充実させるため、産科、小児科、救急医療や、中小の病院への診療報酬を手厚くし、勤務医の過剰労働の緩和をめざし、開業医の夜間診療や往診の報酬を引き上げ、負担を肩代わりしてもらうことなどを柱とした改定を検討していることが明らかになりました。検討案によると、「一定の地域や産科・小児科などで必要な医師が確保できず、医療の提供に支障がでている」とし、地域医療の確保・充実に「特に配慮を行う」と明記。こうした診療科への報酬を手厚くするとともに、医師不足の原因と指摘される勤務医の過剰な負担の軽減を目指す。 (2007/8/8) |
|
 |
3日間の健康診断で210万円!!!東大病院1泊18万円!!! 東京・六本木の新名所「東京ミッドタウン」の「東京ミッドタウンメディカルセンター」の特別メニューに3日間の健康診断で210万円という驚きのコースがあり、3月のオープン以来それなりに利用者がいるというのだから更に驚きだ。もっとも、東大病院の14階特別病室は1泊18万9000円もするが1年365日のうち336日ふさがっているというから、お金持ちっているんですね。格差社会がさらに広がっているようですが、あまりにもいびつな格差のように感じてなりません。 (2007/8/7) |
 |
厚労省、後発薬を標準に薬の処方せん書式変更 厚生労働省は価格が安い後発医薬品の普及を目指し、来年春にも薬の処方せん書式を後発薬の処方を前提とした書式に変更する方針を固めました。現行の書式は、新薬の処方が前提になっており、薬の処方は医師が決めるが、後発薬を選ぶ場合には「後発薬への変更可」という項目に医師が署名する形式です。 (2007/8/6) |
| 長隆氏が総務省『病院懇』座長に!新病院建設に大きな壁! 『自治体病院再生への改革仕掛け人として知られ、小樽の新病院建設で警鐘を鳴らしていた長隆(おさ・たかし)氏が、総務省が新たに設置した、公立病院改革懇談会の座長に就任したことが分かった。長隆氏は、小樽市の進める豪華巨大病院建設は、帰りの燃料なしの戦艦大和の無謀な出撃だと、警鐘を鳴らしていた。』〜以下詳細は『小樽ジャーナル』でごらんください。(2007/7/13) |
|
| 総務相「公立病院改革懇談会」を設置、公認会計士の長隆氏が座長に 菅義偉総務相は、経営難の続く公立病院の改革の進め方を検討する「公立病院改革懇談会」の設置を発表、座長には公認会計士の長隆氏をあて5、6人の委員を選任。公立病院の給与や定員管理の適正化、病床利用率の向上策などを検討。地域医療の再編やネットワークのありかた、経営形態の見直しなどについても協議し、年内に「公立病院改革ガイドライン」を策定する。公立病院を経営している地方自治体には、平成20年度以降に改革プランを策定するよう求める考えだ。(2007/7/13) |
|
 |
札幌中央病院(中央区)再生ファンドと組み不動産を流動化 札幌中央病院(中央区)は、東京の病院再生ファンドキャピタルメディカと組み、病院施設の流動化による経営改善に乗り出した。キャピタルメディカが設けた特別目的会社(SPC)に病院の土地と建物を約8億円で売却し賃貸での利用に切り替え、三菱UFJリースなどからの資金も合わせ約11億円を調達し、北洋銀行からの借入金を返した。金融機関からの借り入れや固定資産税の負担を減らして収支の改善を進め、2010年度にも同市内で病棟を移転新築する計画。 (2007/7/13) |
 |
カプセル型内視鏡を導入 岐阜県笠松町の松波総合病院(山北宜由院長)が、カプセル型内視鏡を導入しました。カプセル型内視鏡は、臨床試験は行われてきましたが、臨床の現場で導入されるのは日本で初めてです。カプセルは長さ26ミリ、直径11ミリ、重さ3.45グラム、先端にカメラが内蔵されている。飲んでから自然に排出されるまで約8時間かけ5万5000枚を撮影。カプセルから送信された画像データを、体につけたセンサーを通じ携帯型記憶装置に受信する。患者は検査をしながら日常生活を送ることができる。カプセルは、専用キットで回収し医療廃棄物として処理する。4月に厚生労働省が輸入販売を認可。開発したイスラエルのギブン・イメージング社の日本法人が輸入し、医薬品卸のスズケン(本社・名古屋市東区)が5月から販売を開始した。価格は、カプセル10個入りが100万円、携帯型記憶装置一式が140万円、実際にデータを取り込んで医師が画像を見る専用のコンピューター一式が503万円。検査はまだ公的医療保険適用外だが、同病院は、希望者に13万8000円で検査を実施、早ければ07年中に保険適用される可能性もあるといいます。 (2007/7/13) |
| 北大、札幌・旭川両医大で、道内勤務条件に奨学金 北海道大と札幌医大、旭川医大は、道内の医師不足を解消するために道内の都市部以外の病院で2年間働くことを条件に医師の資格がある大学院生に奨学金を支給する制度を連携して創設することを決めた。奨学金の支給対象者は医学部(6年間)を卒業後、2年間の臨床研修制度を終えた大学院生。来春は計20人程度、将来的には約100人を見込んでいる。大学院は通常4年間だが、3年目から2年間で1人当たり計数百万円の奨学金を支給する方針。代わりに修了後、道内の都市部以外の病院で2年間勤務してもらうというもの。2年間の都市部以外の勤務が終了すれば、3大学が独自に制定する「指導医」の資格を与えられるもので来春からの奨学金支給を目指す。 (2007/7/3) |
|
 |
市立小樽病院も地域の不足解消へ無料研修 市立小樽病院は結婚や出産、育児などの理由で現場を離れている看護師を対象に職場復帰に向けた無料研修制度をスタートさせた。研修の内容や日程、期間などは、受講者の希望や離職期間などを総合的に勘案して決める。指導は同病院の看護師が行い、受講は無料。研修を受けても、同病院に就職する義務はない。問い合わせは同病院総務課(電)0134・25・1211内線303へ (2007/7/3) |
| 旭医大 市立根室病院へ9月めどに常勤医再派遣へ 医師不足を理由に常勤の整形外科医二人を三月末に引き上げていた旭川医大は、整形外科医一人を常勤医として同病院に派遣することを決めました。非常勤医師を派遣してきた旭医大は、七月一日付で学長が交代し新執行部が発足したのを機に、「建学の精神に立ち返り、地域の医師不足解消に積極的に役立ちたい」(吉田晃敏学長)と常勤医の再派遣を決めたとのことです。地域柄、外科的怪我が多い地区のために少しは安心できたようです。 (2007/7/3) |
|
| 羅臼町立病院、診療所に 根室管内羅臼町の脇紀美夫町長は同町唯一の医療機関である町立国民健康保険病院(四十八床)について、財政難と医師、看護師不足を理由に本年度内にも「無床の診療所にせざるをえない」との考えを明らかにした。同病院は内科常勤医二人、外科の非常勤医一人、看護師十七人の体制だが、七月末までに常勤医一人、看護師四人が自己都合で退職する予定で、後任は見つかっていない。また、診療報酬改定の影響で、入院収益が二○○六年度決算で前年同期比約四割減の約一億三千万円に激減。不良債務も○六年度決算で六億六千万円に上っているということですでに土日と平日夜間の救急を、三月十日で廃止している。 (2007/7/3) |
|
 |
岩内に内科医派遣 4県5病院も 厚生労働省は、国による緊急医師派遣制度の初めてのケースとして、北海道、岩手、栃木、和歌山、大分の1道4県にある6病院に計7人の医師を送り出すことを明らかにした。派遣先は北海道社会事業協会岩内協会病院(内科)、岩手県立大船渡病院(循環器科)、岩手県立宮古病院(循環器科)、栃木県の大田原赤十字病院(内科)、和歌山県の新宮市立医療センター(産婦人科)、大分県の竹田医師会病院(救急)。人数は宮古病院が2人、ほかの5病院は1人ずつ。 これらの病院では医師の退職が相次いだ結果、「5月から内科の常勤医がいない状態が続いている」(岩内病院)、など深刻な影響が出ており、道や県が派遣を要請していた。派遣する医師は国立病院機構や日本赤十字社などから選ばれ、八月ごろまでに着任、派遣期間は3-6カ月間で、2-3週間ごとに別の医師と交代する。岩内協会病院に派遣されるのは中京病院(名古屋市)の高口裕規医師(34)。 (2007/7/3) |
| 財団法人日本医療評価機構の5月28日新規・更新認定道内分は、心臓血管センター北海道大野病院(西区)がV5.0で更新取得、くにもと病院(旭川)が新規で取得いたしました。道内の認定病院は116医療機関となりました。 (2007/7/2) | |
 |
最近はTVでもゲームでも脳神経トレーニングが大流行、更に動体視力を鍛えるゲームも 最近は、ゲーム機では任天堂のWiiが大流行です。どうやら、コントローラーの使い方の新しい提案と脳年齢を測定しトレーニングするということが、若者と同時に年配者にも大うけしたようですね。高性能のハードウェアで対抗したソニーもこれには敗退したようですね。パンダに勝った旭山動物園というところかな?脳の活発化の為には歩く、かむという連続的周期運動より、物をつかんだり、ボールをける断続的離散運動の方がより良いといわれています。これはMRI(磁気共鳴画像化装置)を使って脳の活動の程度を調べた結果でも判明しています。つまり、離散運動を積極的に導入することで、効果的なリハビリに応用できるということのようです。 (2007/6/25) |
 |
ホスピタルローソンの次はコーヒーチェーンのスターバックスが KKR札幌医療センター(豊平区)や北斗病院(帯広)、北斗クリニック(帯広)では既にローソンを出展しており、新築に合わせて新規にオープンした北海道社会事業協会富良野病院とともに24時間対応と品揃えに優れたノウハウを持っているローソンの進出が目立ってきていますが、旭川医科大学(旭川)や札幌医科大学医学部付属病院(中央区)などでは大手コーヒーチェーンのスターバックスが病院内店舗として参画してきました。こういった差別化による競争の優位性の確保は今後も続くものとおもわれます。 医師/環境 1 (2007/6/18) |
| 勤医協 札幌病院(東区)で女性専用外来が開設されました。毎月第1−3月曜日、午後の完全予約制です。 女医さんがいる医師/環境 (2007/6/18) | |
| 札幌・旭川両医大で「地域枠」10人、道内勤務条件に奨学金 北海道医療対策協議会は、道内の自治体病院などでの勤務を条件にした「地域枠」の原案をまとめました。「地域枠」の学生には奨学金が支払われ、その原資は道と市町村で折半するが地域枠の対象は道内高校卒業者。同枠の医大生には卒業後、2年間の初期研修を含めた9年間、地域医療での従事を義務付ける。また、派遣先は道医対協が調整するということになります。札幌医科大学と旭川医科大学が早ければ来春の入学生から5人ずつ募集するということです。旭川医大は08年度からこれとは別に新たに5人の枠を設ける。 北海道大学は「総合大学として調整が難しい」と判断し、地域枠の設定を見送る模様。 (2007/6/13) |
|
 |
病院統合:美唄の市立美唄病院と美唄労災病院が来年4月めどに厚労省と本格協議へ 市町村の公立病院と労災病院が統合されるのは、全国で初めてということですが、本年度末で累積債務が二十二億円に達する見込みの市立病院の立て直しを厚労省の労災病院再編計画で岩見沢労災病院と美唄労災の本年度中の統合案が示されており、道内唯一の「勤労者腰痛・脊損センター」の機能の存続を強く要望されていた両院の要望を受け存続させる方策として、市立病院との統合を選んだということになりました。市と同機構は(1)両病院を来年4月を目途に統合(2)新病院は労災病院の施設を利用して市が運営する(3)労災病院が行っている「せきつい損傷医療」を引き継ぐ機構側は医師を派遣し支援する----などの内容、合意した。 (2007/6/13) |
| 登別・三愛病院が病院案内等の活字文書読み上げ装置導入 登別市の三愛病院では視覚障害者や高齢者に配慮し、病院案内などを音声で聞くことができる「活字文書読み上げ装置」を導入しました。同装置は文字情報を記録した音声コードを近づけると、読み上げる仕組みということです。詳しくは、室蘭民報ニュースにて紹介されています。 (2007/6/13) |
|
 |
脳卒中上肢機能障害に有効なCI療法 兵庫医科大病院が先駆的に導入 脳卒中の上肢機能障害に対する積極的リハビリテーション治療として、「constraint induced movement therapy(CI療法)」が世界的に注目されて、日本の「脳卒中治療ガイドライン」にも推奨度は「グレードA」に位置付けられています。先駆的にCI療法を導入している兵庫医科大病院では、高い効果をしめしています。脳卒中のリハビリテーション医療は近年、神経科学や脳科学の研究成果を取り入れて大きな進歩を遂げていますが、その1つが脳の可塑性に着目したCI療法で急性期から慢性期に至るまで効果が確かめられています。CI療法とは、片麻痺上肢の健側の運動を三角巾などで制限し、患側の運動を誘導する治療法のことですが、現在のところほとんどのリハビリ病院では、健側による代償訓練の利き手交換が偏重されており、片麻痺上肢のリハビリは切り捨てられている状態が続いています。神経科学や脳科学など基礎研究の成果もリハビリ医療にまったくといっていいほど反映されていないのが現状です。このため、日本でCI療法を導入している病院はごくわずかでしたが庫医科大病院では、神経科学などの進歩をリハビリ医療に積極的に臨床応用する方針を打ち出し、CI療法については2003年から本格導入していました。治療は基本的に自主訓練で、作業療法士が適宜指導する。患者にとっては麻痺した手を強制的に使わざるを得ないため、想像以上に過酷な訓練となる。しかし、患者の自覚的満足度も高く、治療を受けた患者からは」「積極的な気持ちになった」「麻痺側を意識的に使うようにしている」「積極的に生きる望みが得られた」などの声が寄せられています。こういったことから、治療を希望する患者が全国から殺到しているとのことです。医業収入としては、病院側にとっては経営的にあまりプラスにはならないために二の足を踏む状態にもなっている。 CI療法の今後の可能性については、海外での臨床報告から、脳卒中の上肢機能障害以外に、脳外傷・脳性麻痺・局所性ジストニア・幻肢痛・失語症・脳卒中による下肢麻痺・脊椎損傷などへの応用拡大も期待できるとしている。(2007/6/7) |
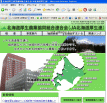 |
道内病院、総合診療を拡充 道内病院があらゆる患者の初期診療を担う「総合診療」の拡充にスタート北海道厚生農業協同組合連合会(道厚生連)は札幌や旭川で運営する6病院に総合診療科を設ける。すでに帯広厚生病院(帯広市)と倶知安厚生病院(後志管内倶知安町)には設置済みだが、医師の不足状態を緩和し地域の医療体制を再構築するには他の病院に広げる必要があると判断し2011年までに体制を整える計画。6病院でそれぞれ約5人の総合医を確保したい考え。勤医協中央病院(札幌市)などは総合医の育成を本格化する。 (2007/6/5) |
| 3医師の保険医取り消し 北海道社会保険事務局は水増しして診療報酬を不正請求したとして、道内の診療所1施設と医師3人に対し、6日付で保険医療機関指定と保険医登録をそれぞれ取り消すと発表しました。対象者らは、同日から5年間保険診療ができない。取り消しの対象となった医療機関は後志・寿都町の磯谷診療所。医師は同診療所の中西均所長(60)と、函館市内の歯科医院(昨年9月廃止)で診療していた牧浦一元・元院長(65)、角川進次郎医師(53)の計3人。 (2007/6/5) |
|
| 室蘭太平洋病院(室蘭)が「物忘れ外来」を開設 室蘭市白鳥台の室蘭太平洋病院(室蘭)が専門外来「物忘れ外来」を開設しました。診療は問診や知能テスト、脳の画像検査など複数の検査を実施し加齢による正常な物忘れか、認知症を引き起こす病気があるかなどを探り、治療につなげるものです。 ・専門外来 (2007/6/5) |
|
| 副院長に看護師 看護師を副院長に起用する病院が急増。全国病院事業管理者等協議会の調査では、今月1日時点で3年前の3倍超に当たる168施設で看護師が副院長に就いています。看護師を病院運営の要職に据えることで患者本位の医療を目指すということで独立行政法人化や赤字経営などで改革を迫られた大学病院や公立病院で多くなっているようです。 (2007/6/5) |
|
| 道庁に医師確保推進室 医師不足問題への対応策として道庁に医師確保推進室ができ、今年度中に、5人の"道職員医師"採用を目指すとしています。再選直後の記者会見で高橋はるみ知事が設置を表明した医師確保の専門組織で従来の大学の医局から派遣されてきた仕組みに変わって道が独自に医師を採用・派遣する仕組みで道職員としての身分を保障した上で、2年間は医師不足病院に派遣し、1年間は有給で、希望する研修を約束しようというもののようです。一部の医師たちからは、短絡的との批判もありますが、取り組んでいくということが大切です。その中で、問題は改善していかなければ先には進まないでしよう。これからも、次々と取組んでいって欲しいものです。 (2007/6/4) |
|
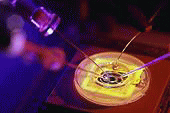 |
人工臓器と移植医療の限界を打破するこれからの再生治療への期待 再生医療について当サイトでもできるだけお知らせしていますが、ここには今まで中心となっていた人工臓器と移植医療の限界が見えて来たということがあげられます。人工臓器は一時的な代用にはなりますが長期間の使用は生体適合性の問題を克服してはいませんし動力の小型化も大きな問題となっています。移植医療は、免疫抑制剤の登場や技術の進歩により格段の進歩を遂げ、現在中心となっています。しかし、臓器提供者の問題が大きく全ての人たちの対象とはなかなかなりません。また、パーキンソン病や脳梗塞などの中枢神経系疾患の患者に対しては対応のしようがありません。患者自身から採取した幹細胞を用いて、疾患部を再生させるという新たな治療の道が再生医療の道です。臨床応用が進んでいるのが、心臓ですが、毎日のように新しい情報が入ってきます。非常に困難だといわれていた神経系の代謝障害にも再生医療の応用の研究が始まっています。今の段階では、研究が始まったばかりですが倫理面の問題も発生するのですが、多くの期待を抱かずにはいられません。 (2007/5/30) |
 |
再生医療へ大きな前進、理研・神戸研究所でヒトES細胞の大量培養に成功 体の様々な組織の細胞になる能力があるとして再生医療に大きな期待をもたれている人の胚性幹細胞(ES細胞)だが、培養が難しく十分な細胞量を確保できず、研究や将来の治療に使うのに支障になっていましたが、理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(神戸市)の笹井芳樹・グループディレクターらの研究チームがES細胞を大量に増やすことができるうえ、脳こうそくや神経難病の治療への応用が期待できるなど、再生医療の実現に大きく近づく成果をあげました。治療応用までには安全性や倫理面でのルールづくりなど、問題もあるでしようが画期的な成功ですよね。 (2007/5/28) |
| 医師不足対策として国公立大に地域枠も 政府・与党が検討している緊急の医師不足対策が明らかになりました。中長期的対策では、国公立大学の医学部に臨時の定員増を認め、「地域枠」も拡充し医師の養成数自体を増やしていくとともに卒業後も一定期間、地元で勤務することを約束した学生には奨学金を支給する方針。当面の対策としては、「国レベルで緊急の医師派遣体制を整備する」とした。都道府県からの要請に応じ、国立病院を管轄する国立病院機構や全国ネットワークを持つ病院から、数カ月〜1年程度、各地の自治体病院などに医師を派遣する。定年退職して間もない医師に呼びかけるなどして医師を確保する。勤務医の過重労働を緩和するために職場環境を整備し役割分担を見直すなどして改善していくとともに医療事故の補償制度や、医療中に死亡した患者の死因調査制度も早期に実現し、医師の訴訟リスクなども軽減を目指すという。(2007/5/28) |
|
 |
診療科名に「総合科」新設案 厚生労働省は、医療機関が名乗ることのできる診療科名に「総合科」を新たに加える案を専門部会に示しました。現在、医療機関が広告の際に掲げることが認められている診療科名を分かりやすく整理する中で、開業医など、かかりつけ医の診療科として確立していこうという考え方。今までは、プライムケア(初期診療)医と呼ばれていたものをよりわかりやすく表現したもののようです。医師の専門分野化が進み、どこにいったらいいのかわからなくなっているケースが確かに増えています。当サイトにもそういったご相談が見られます。 また、広告することが現在認められている34の診療科名について、内科や外科、小児科など基盤的な診療科名を18にしぼり、これに「病理診断科」「臨床検査科」「救急科」「総合科」を加え、計22に。専門の領域について、身体の部位や症状、患者の特性、治療技術などに関し、原則自由に表記できるとしています。 (2007/5/28) |
| 財団法人日本医療評価機構の4月23日新規・更新認定道内分は、札幌マタニティ・ウィメンズホスピタル(北区)、石橋病院(小樽)がV4.0新規で独立行政法人北海道がんセンター(白石区)がV5.0で更新取得、函館中央病院(函館)が新規で取得いたしました。道内の認定病院は115医療機関となりました。 (2007/5/22) | |
| 焼尻島の診療所長に技監自ら赴任 道は6月1日付で道保健福祉部幹部の貞本晃一技監(54)=内科医=を留萌管内羽幌町・焼尻島の道立焼尻診療所長とする人事を決めた。後任の医師が決まるまで、医師1人、看護師1人の小規模施設で島民約330人の健康を診ることになる。現在同診療所に勤めている医師は、常勤外科医がいなくなった根室市立病院に派遣されることが内定していた。ところが、この医師の後任が確保できず、窮余の策として貞本技監が自ら手を挙げたという。技監は医療分野で部長を補佐する幹部で、現場の所長になるのは異例。 (2007/5/19) |
|
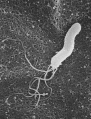 |
北大教授らがヘリコバクター・ピロリ菌による胃の粘膜破壊の仕組みを解明 北海道大遺伝子制御研究所の畠山教授(分子腫瘍学)らの研究グループが、胃がんの原因とされるヘリコバクター・ピロリ菌による胃の粘膜破壊の仕組みを解明し、英科学誌ネイチャーに発表しました。ピロリ菌が作るタンパク質が、粘膜の細胞同士を結合させる酵素の働きを阻害すると判明、その為に胃炎や胃かいようが引き起こされるという。 (2007/5/19) |
| 医師不足で医学部に「地域勤務枠」授業料を免除 政府、与党は、へき地や離島など地域の医師の不足や偏在を解消するため、すべての都道府県の国公立大学医学部に、卒業後10年程度のへき地での勤務を義務付ける枠を設ける方向で調整に入りました。また、定員100人当たり5人程度を「へき地枠」として全国で約250人の定員増員する案が上がっています。地域枠のモデルとなるのは、1972年に全国の都道府県が共同で設立した自治医科大学(栃木県下野市)だ。同大では、在学中の学費などは大学側が貸与し、学生は、卒業後、自分の出身都道府県でのへき地などの地域医療に9年間従事すれば、学費返済などが全額免除される。医学部を卒業した学生にへき地勤務を義務づけることは当初、「職業選択の自由に抵触する恐れがある」との指摘もあった。だが、「入学前からへき地勤務を前提条件とし、在学中に学費貸与などで支援すれば、問題ない」と判断したとのことです。(2007/5/14) |
|
 |
小児・産科に診療報酬厚く 厚生労働省は小児科、産科の医師不足問題に対応するため、関連する診療報酬を2008年度の改定で引き上げる検討を始めるまた、地方の医師不足解消のため、都市部などで院長になる要件に「へき地での診療経験」を含めることも検討。(2007/5/14) |
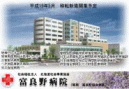 |
北海道社会事業協会富良野病院(富良野)移転新築となりました。また、HP以外にも「ブログ」がありますよ。最近は、このようにHPと更新の楽なブログとの併用が増えてきていますね。 施設/設備1(MRI CT ESWL) (2007/5/14) |
 |
緑茶1日5杯で脳梗塞死亡リスク軽減 緑を1日5杯以上飲むと脳梗塞の死亡リスクが男性は42%、女性は62%低下するとの研究結果を栗山進一東北大准教授らが発表しました。緑茶に含まれるカテキンなどが体に良い影響を与えている可能性があるということのようですが、昔はお茶は薬として大切にされていましたが、やはり身体にいいようですね。 (2007/5/9) |
 |
「ドクターヘリ」法案参院厚生労働委員会で全会一致で可決 「空飛ぶ救命室」とも呼ばれる「ドクターヘリ」の全国展開をめざす特別措置法案が参院厚生労働委員会で全会一致で可決され、今国会での成立をめざす。へき地や離島の医師不足対策としても期待されており、僻地の自治体病院からの医師の引き揚げが続いている現状は追い風となっているのだろうか?。 (2007/5/5) |